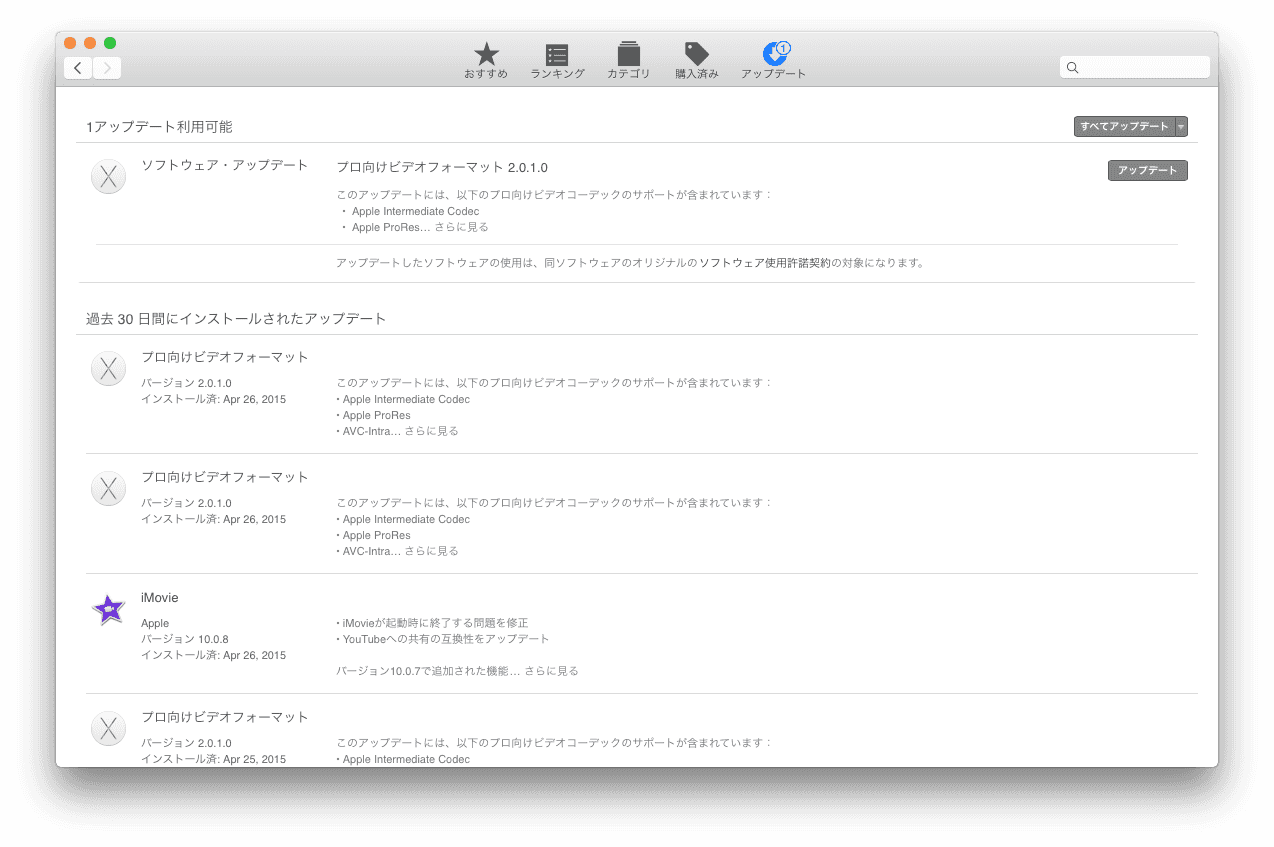ところが当の大学の地質学教室では、「プレートテクトニクスはまだ確定した理論ではない」として、古い「地向斜造山論」が80年代半ばまでまかり通っていたというのだ。世界の地球科学の学者間で、プレートテクトニクス理論がスムーズに受け入れられたのとは対照的に、日本でのパラダイムシフトが遅れた原因として「地団研」の存在があったと、泊次郎「プレートテクトニクスの拒絶と受容」は指摘している。私はこの本を読んで、当時の地質学をめぐる環境についてどれだけ無知であったかを知り、また、科学者が合理性から逸脱して血迷ってしまう要因についても考えさせられた。
地団研:地学団体研究会とは、学会であり活動体でもある。目指したのは「科学の民主化」であり、「民主化」とは「レーニン・マルクス主義、あるいはスターリン主義」に基づく、プロレタリアに牛耳られた研究組織からの開放であり、強力なリーダーの統率による団体研究の達成である。この団体の活動には功罪があり、研究費予算の配分、日本列島の効率的な地質研究、学校教育における地学の普及などに成果をあげた反面、地質学研究に関して鎖国的な対応とこの著者の言うところの歴史法則主義への固執という負の側面があった。
プレートテクトニクスの概念が誕生する前、海底の堆積物がアルプスやヒマラヤのような高所にまで押し上げられる原動力は謎であった。そこで提唱されていたのが「地向斜モデル」と「地球収縮説」だ。大陸のヘリにくぼみができ十分な堆積物が溜まる。ある時期に地球が冷えて収縮すると、地球表面にはシワがよって堆積物が山となって盛り上がる、という説である。現代の地球科学において(これは私が学生だった1982年頃でさえすでにそうであったはずだが)、「現在地球で起きていることは過去にも起きていたことであり、過去に起きたことは現在も引続き起こることである」という考え方が基本スタンスになっている。ところが、「歴史法則主義」はそのように考えない。地球は歴史を積んで現在に至っているのであり、事象は「始まりがあり、継続期間があり、そして終息する」というスタンスをとる。歴史法則的観点から解釈すれば、堆積物は長い期間地向斜が沈降しながら厚みを増やし、地球規模で造山活動が始まると隆起し、やがてその活動が終わると侵食されていくというサイクルを想定した。地団研では日本列島の地史を組み立てるにあたって、地向斜は花崗岩の浮力により独自に隆起するというモデルを用いてはいたが、「アルプス造山運動」という用語もしばしば見受けられ、地球規模の造山活動という観点は捨てられなかったようだ。そして現在見られる高い山は、古生代や中生代に起きた過去の造山運動の遺物であると考えるのだ。
確かに高校までの教科書にはこのようなことが書いてあったような気がする。そして、火山についても「活火山」「休火山」「死火山」というような区別をしていた。これも始まりがあり、継続期間があり、終りがある、という歴史法則的な見方と言える。
実際にはそうじゃない。高い山は現在も隆起しているから高い。火山として形をなしているものは現在も活動中だ。その現実を見事に説明できたのがプレートテクトニクスのモデルであり、1960年代の半ばには世界中で受け入れられ始め、そのモデルに基いてさまざまな検証がなされてきた。驚くべきはこの新しいパラダイムに対する地団研のとってきた態度だ。なんと1980年代も半ばとなるまで、かたくなに独自に発展した地向斜造山論に固執し続けたのだ。
私が高校生のころに読んだ「野尻湖の発掘」「化石」「日本列島」などの著者、井尻正二や湊正雄、大学受験の地学の参考書の著者、牛来正夫は、いずれも地団研の大御所だ。特に牛来先生は東京教育大学の岩石学の教授だった。東教大が筑波移転となる際、牛来先生は移転を拒んだらしい。もっとも東教大の筑波移転は、左翼にとって当局による不当国家権力行使だったので拒むのも無理からぬことだが、そのおかげで私は地団研と系統の異なる、東大系統の岩石学の教育を受けることとなった。牛来先生は初源マグマの結晶分化モデルにも疑問を持っておられたようだし、その後「地球膨張説」など唱えていたそうで、それを思うと私は学問的に幸いだった。
しかし、何が科学者の目をここまで曇らせるのだろう。プレートテクトニクス以前、地向斜造山論はきわめて論理的に説得力のある説であり、それに基いて日本の地質や地史を読み解くは先端であり合理的だったのは間違いない。しかし、一旦それで体系が仕上がってしまうと、新しいもっと合理的なパラダイムが登場した際に破棄できなくなってしまうのは純粋に心情的な側面に見える。そしてその心情的な部分を後押しするのが「思想」なのだろう。地団研の場合、マルクス・レーニン主義、あるいはスターリン主義がそれだ。(やがてその左翼思想もソ連の崩壊とともに瓦解することになるが。) 自然科学は合理性を求めるものだが、人間はなかなかそうはいかない。左翼思想も戦後においては先端思想であり、東京でも革新都知事の時代があった。人の生き方に直結する分、若いころに染まった思想はなかなか捨てられない。これが老害だ。組織は人が作るもの。組織が育つにつれて古い人は権威となり、そして組織は老害によって合理性を失って行く。自然科学といえども研究をする主体が人間であるかぎり、その人間性の束縛から逃れられないということだ。
ところで、私が地球科学を学びたいと思ったきっかけになったのは「日本沈没」だけではない。それよりももっと前に父が与えてくれた一冊の絵本、バートンの「せいめいのれきし」との出会いが大きい。宇宙、太陽系、地球の誕生から、様々な生きものが地球上に現れては消え、そして人類の時代になり、自分の祖先から現在の「私」の生活に至る壮大な物語だ。1962年に初版となるこの絵本、実は地球収縮説で山のでき方が説明されていた。私の生まれた年だ。いしいももこの訳で日本で出版されたのが1964年。この時点でプレートテクトニクスはようやく有力なモデルとして一部の注目を集めるようになった。そして10年そこそこのうちに小松左京が日本沈没を書くことになる。急激なパラダイム・シフトだったわけだ。それと同時期に、日本の地質学者は地向斜造山論に基いく日本の地史の集大成を作り上げていたのだと思うと、人間のいとなみの虚しさすら感じる。
ちなみに、昨年、「せいめいのれきし」は最新の地球科学の学説を(ようやく)取り入れて改訂版が出版された。原著はとっくのむかしに(おそらく1990年代に)改訂されてたので、こんなところでも日本はプレートテクトニクスの受容が遅れてしまってた。ようやくの改訂がうれしくて、親戚や知り合いの子供に贈った。この本をきっかけに、地球科学に興味をいだいてくれると嬉しいな。